訪問看護とは、病気や障害を持つ人が住み慣れた地域や自宅で、その人らしい療養生活を送ることができるよう、支援するサービスです。訪問看護は、1992年に訪問看護ステーションが創設され、制度や報酬の仕組みの基本ができました。その後2000年に介護保険制度がスタートし、訪問看護は医療保険と介護保険の両方の制度を利用して運営されています。診療報酬は2年ごと、介護報酬は3年ごとに改定され、5年ごとに両方の報酬の改定が同時に行われることになり、少しずつ制度が変わってきています。このように訪問看護の制度は複雑化してわかりにくくなりつつある現状ですが、サービスを提供する側はその制度や報酬の仕組みを正しく理解し、活用していかなければなりません。今回はこれらの制度や報酬の仕組みについて、基本をご紹介します。
医療保険と介護保険の違い
日本の社会保険には年金保険、医療保険、介護保険、労働者災害補償保険(労災保険)、雇用保険の5つがあります。このうち、訪問看護に関わってくるのは医療保険と介護保険です。
①医療保険
医療保険制度は、すべての国民に医療サービスを提供するためのもの。国民全員が強制加入となり、保険料を納付する代わりに、保険証を提示することで一定割合の自己負担額で医療行為を受けることができます。
自己負担の割合はかかった医療費の3割が原則ですが、義務教育前の子どもは2割、70歳~74歳は2割または3割(所得が現役並みの場合)、後期高齢者医療制度の対象となる75歳以上は1割または3割(所得が現役並みの場合)となります。
②介護保険
介護保険制度は2000年から実施されている、新しい社会保険の制度です。寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができるとされています。
介護サービス事業者が提供する在宅や施設での介護サービスを、一定割合の自己負担額で受けられます。自己負担の割合は、所得に応じて1割、2割、3割のいずれかとなります。
40歳以上から加入となり、保険料は所得水準に応じて決まります。医療保険の保険料と一括して徴収される(40歳~64歳)場合と、公的年金から天引き(65歳以上)される場合があります。
2つの保険の決定的な違いは、介護保険を利用するためには認定が必要ということ。利用前に市区町村が調査して要介護度を判定し、ケアマネジャーがサービスの利用計画を策定する必要があります。
医療保険の給付方法と種類
医療保険の給付の方法は様々です。もっとも一般的なものは、診察や投薬、治療、手術、入院などの医療を受けた際、保険証を提示して一部負担金を支払う「療養の給付」という形です。
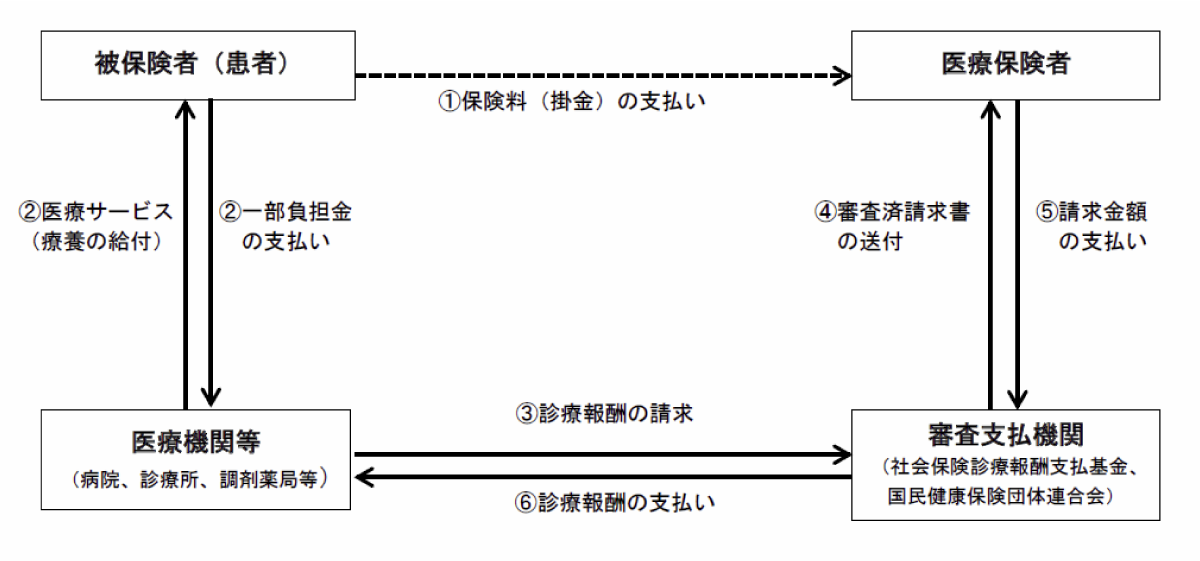
このほかに主な医療保険として、
・訪問看護療養費・家族訪問看護療養費
訪問看護師から療養上の世話や必要な診療の補助を受けた場合に給付されます。
・入院時食事療養費
入院時に食事の提供を受けたときの食費の一部が支給されます。
・高額療養費
高額な療養費のうち限度額を超えた分が払い戻されます。
・高額介護合算療養費
同一世帯で医療保険と介護保険の1年間の自己負担額の合計が限度額を超える場合に払い戻されます。
・移送費
治療のために緊急に移送されたときに実費が払い戻されます。
・傷病手当金
業務外の事由による病気やケガの療養のため、連続する3日間を含む4日以上仕事に就く事が出来ず、十分な報酬(給与)が得られない場合に、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
・出産育児一時金
被保険者及びその被扶養者が出産したときに、1児につき支給されます。
・出産手当金
被保険者が出産のため会社を休み、その間に給料与の支払いを受けなかった場合に、出産の日以前42日から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。(双子以上の多胎、出産予定日と出産日が異なる場合は上記期間が異なります)
・埋葬料
死亡したときに支給されます。
などがあります。
※保険給付の種類と内容 | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
このうち、訪問看護に深く関わりある訪問看護療養費・家族訪問看護療養費について説明しましょう。
訪問看護療養費も療養の給付と同様、全国健康保険協会や市区町村などの保険者が、指定訪問看護事業者に費用を直接支払うことになっています。患者は指定訪問看護事業者に3割負担となる基本利用料を支払います。
このほかに患者からは、交通費・おむつ代などの実費、営業時間外の対応といった特別サービスを希望して受けた場合の特別料金を、その他の料金として徴収することがあります。指定訪問看護事業者は、基本利用料とその他の料金について区別した領収書を発行することになっています。
さらに、訪問看護療養費の基本利用料は「高額療養費」の対象となりますので、それについても算出方法など詳しく知っておく必要があります。
同一月内の医療費の自己負担限度額は、年齢および所得に応じて計算式が用意されており、それを超えた額が高額療養費として払い戻されます。この計算は全国健康保険協会や市区町村の医療保険のWebサイトで確認できます。
介護保険の給付方法と種類
介護保険の保険料の納付と介護報酬の支払いの流れを見てみましょう。

介護保険制度の保険者は市区町村です。介護保険サービスの給付に関わる要介護認定がなされた場合、介護保険被保険者証が交付されます。対象となるのは65歳以上と、40歳以上65歳未満で特定疾病を持つ人です。
特定疾病とは、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し、次の16種類に該当する疾病です。
・がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
要介護認定は、介護の度合いに応じて「要支援1~要支援2」「要介護1~要介護5」の7段階に分けられます。
要支援・要介護度別に支給限度額が決められていますので、その範囲内で支給されます。当然、要介護5が最も高い支給限度額となります。
ただし、同一世帯の利用者が支払った1ヶ月ごとの利用者負担額の合計が一定の上限を超える場合は、申請により「高額介護サービス費」として超えた額が支給されます。
訪問看護師は、報酬に関わる重要な要素となりますので、療養者がどの区分に当てはまりどの給付を受けられるのか、説明できるようにしておきましょう。
参考:「訪問看護師のための診療報酬&介護報酬のしくみと基本」(メディカ出版)



 コラム一覧へ
コラム一覧へ



